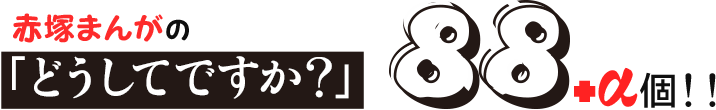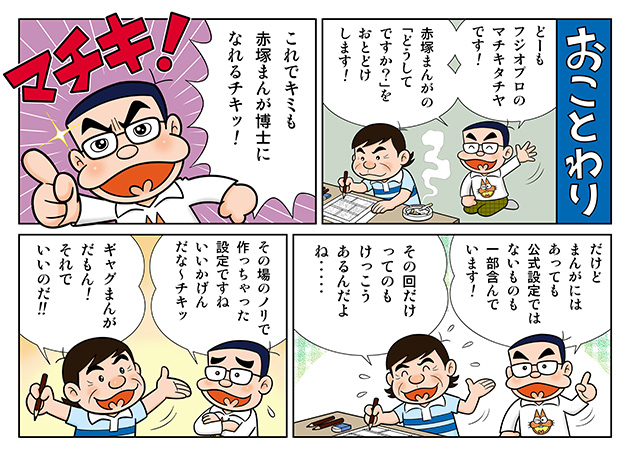- 六つ子を見分けるためにおとうさんはどんな工夫をしましたか?
- 六つ子のおかあさんの苦労を教えてください。
- 松野家のごはんを紹介してください。
- 六つ子のおかあさんにモデルはいますか?
- 六つ子のおとうさんの仕事は何ですか?
- 六つ子の部屋はどんな部屋ですか?
- 六つ子のなかで美意識が高いのは誰ですか?
- いろんな人が「シェーッ!」をしていますが、今までどんなスゴイ人が「シェーッ!」してますか?
- イヤミがシェーをするとき、いつもくつ下がびろーんとなっているのは、どうしてですか?
- イヤミに奥さんはいますか?
- イヤミはフランスで何をしていましたか。
- チビ太はどんなアルバイトをしていますか。
- チビ太に子分はいますか?
- チビ太がいつも持っているおでんの具を教えてください。
- トト子ちゃんについて詳しく教えてください。
- トト子ちゃんはだれがいちばん好きですか?
- デカパンのパンツには何が入っていますか?
- ハタ坊の旗の由来を教えてください。
- チビ太が主人公になったお話を教えてください。
- おそ松くんの「チビ太の金庫やぶり」には、いくつかのバージョンがあると聞きました。詳しく教えてください。
- 「もーれつア太郎」のタイトルはどうやってつけられましたか。
- ア太郎は学校に行っていますか?
- ア太郎にガールフレンドはいますか?
- デコッ八は、どうしてア太郎といっしょに働くことになったのですか?
- デコッ八に惚れるお話を教えてください。
- ×五郎はどうして幽霊になったのですか?
- 神様はいますか。
- ニャロメはどうして人気者になりましたか。
- ニャロメの名前の由来を教えてください。
- ニャロメはどこに住んでいますか?
- ニャロメはすぐに女の子を好きになりますね?
- ニャロメが不良になったお話を教えてください。
- ブタ松は人間ですか? ブタですか?
- ブタ松に子分はいますか?
- ココロのボスは、人間ですか? タヌキですか?
- ココロのボスに子分はいますか。
- ココロのボスの口ぐせは何ですか?
- デコッ八の妹について教えてください。
- カエルのべしの名前はどうやって付けられましたか?
- タイトルの「バカボン」の意味を教えてください。
- 「天才バカボン」の主人公は、誰ですか?
-
バカボン一家の苗字を教えてください。
一家の家に「バカボン」という表札がかかっているのを見たことがありますが、「バカボン」が苗字ですか? - バカボンのパパは何歳ですか?
- バカボンのパパは働いていますか?
- バカボンのパパとママは、いつ、どこで出会ったのですか?
-
バカボンのパパの鼻の下にあるのは、ヒゲですか? 鼻毛ですか?
それから頭にあるのはハチマキ?それともリボン? - バカボンのパパの本名が田中田フチオと聞いたことがありますが、本当ですか?
- バカボンのパパが嫌いな食べものを教えてください。
- バカボンのパパは、いつからバカになったのですか?
- バカボンのパパは、何座ですか?
- バカボンのパパのセリフに「わすれようとしても思い出せない!」というのがありますが、これはどういう意味ですか?
- バカボンのパパの泣き顔を見せてください。
- バカボンのパパはバカ田大学の出身ですが、中学校や高校は、どこに通っていたのですか? また、出身地はどこですか?
- バカボンは、何歳ですか? 学校に通っていますか?
- ハジメちゃんは、次男なのにどうして 「ハジメ」という名前なのですか?
- ハジメちゃんは、いつから天才だったのですか?
-
目ン玉つながりのおまわりさんの名前を教えてください。
ついでに息子の名前も教えてください。 - 目ン玉つながりのおまわりさんの目玉は、最初は繋がっていなかったと思うのですが、いつ、どうして繋がったのですか?
- レレレのおじさんのこどもは何人いますか?
- いつもやさしいレレレのおじさんですが、怒ることはありますか?
- レレレのおじさんの職業は何ですか?
- レレレのおじさんの鼻の下あたりにあるのは、ヒゲですか? 汚れですか?
- ウナギイヌの誕生エピソードを教えてください。
- ウナギイヌはどうして人間の言葉を話せるのですか?
- ウナギイヌはイヌですか? ウナギですか?
- ウナギイヌはどこに住んでいますか?
- カメラ小僧のモデルは篠山紀信さんですか?
- カメラ小僧は子どもですか? おとなですか?
- 「ホッカイローのケーコターン」と叫んでいるキャラクターについて教えてください。
- バカ田大学では、どんな勉強をしているのですか?
- バカ田大学には、女子学生も在籍していますか?
- 天才バカボンで「実験まんが」といわれるものを教えてください。
- 片手で逆立ちをしているイヌについて教えてください。
- 「天才バカボン」の最終回はどうなりましたか?
- 赤塚センセイは大の映画好きだと聞きました。お気に入り作品や監督を教えてください。
- 赤塚まんがのなかで映画や小説からヒントを得たお話はありますか?
- 漫景って何ですか?
- 「シュールな作品」とはどういう意味ですか?
- 赤塚まんがに登場する言葉が話せる動物キャラを教えてください。
- 赤塚まんがでは、一度死んだひとや動物がまた元気に登場することがよくありますが、どうしてですか?
- チビ太のほっぺたにあるヒゲのようなものは何ですか?
- バカボンやハジメちゃんの ほっぺたにあるうずまき模様は何ですか?
- 赤塚まんがのキャラクターの口のなかには、ハートマークのようなものが見えますが、あれはのどちんこですか?
- 赤塚センセイがギャグやストーリーを考えるときに影響されたものを教えてください。
- 赤塚センセイは、手塚先生をとても尊敬されていたと聞きましたが、手塚作品のなかで特に思い入れの深い作品を教えてください。